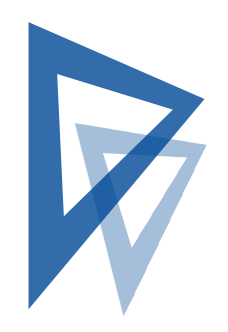第7回バイオインダストリー大賞 特別賞受賞者インタビュー
 今年で第7 回を迎えるバイオインダストリー大賞。その中で特別賞はバイオインダストリーの発展のために新しい分野を拓き、卓越した新価値創出業績に対して、大賞の評価軸とは異なる局面で評価を行い、特別に授与するに該当する場合に与えることができるものとして2021 年に創設された。6 月に開催された選考委員会にて、「コレステロールエステラーゼ大量生産スマートセルの開発」の業績に対し、小西健司氏を代表者とする旭化成ファーマ㈱(以下、旭化成ファーマ)と(国研)産業技術総合研究所(以下、産総研)の共同研究グループに特別賞を授与することを決定した。7 月20 日に特別賞受賞者に対するインタビューを実施し、研究開発のエピソードや創薬への熱い想いを語っていただいた。
今年で第7 回を迎えるバイオインダストリー大賞。その中で特別賞はバイオインダストリーの発展のために新しい分野を拓き、卓越した新価値創出業績に対して、大賞の評価軸とは異なる局面で評価を行い、特別に授与するに該当する場合に与えることができるものとして2021 年に創設された。6 月に開催された選考委員会にて、「コレステロールエステラーゼ大量生産スマートセルの開発」の業績に対し、小西健司氏を代表者とする旭化成ファーマ㈱(以下、旭化成ファーマ)と(国研)産業技術総合研究所(以下、産総研)の共同研究グループに特別賞を授与することを決定した。7 月20 日に特別賞受賞者に対するインタビューを実施し、研究開発のエピソードや創薬への熱い想いを語っていただいた。
左から酒瀬川 信一 氏、安武 義晃 氏、小西 健司 氏、村松 周治 氏、田村 具博 氏
小西:このような名誉ある賞をいただけることになり、研究グループを代表し大変有難く思います。学術的な面と、それが製品化につながったところの事業化面の両面が評価されたことが特に嬉しく思いました。
酒瀬川:受賞が決まり、本当に驚きました。まさか今年いただけるとは思っていませんでしたから、感謝の気持ちで一杯です。
受賞業績の研究が始まったきっかけ
田村:最初に本研究の背景をお話しします。旭化成ファーマと産総研とで2007 年から共同研究を始めており、本研究の前身の研究まで遡ると非常に長い期間です。2007 年当時、産総研では放線菌を宿主としたタンパク質の生産系構築に係る研究を行っており、充分量のタンパク質生産ができなくて困っている旭化成ファーマの課題と一致し、ぜひ一緒に創りましょう、となったのが共同研究の発端です。研究を開始して以降、タンパク質生産で実用化に成功するなど成果を上げてきた矢先、2016 年にNEDO の「スマートセルプロジェクト」(以下、プロジェクト)に参画するにあたって、「新たなテーマでチャレンジしよう」と開始したのがこのコレステロールエステラーゼの大量生産に係る研究です。 共同研究を進める中で、旭化成ファーマは旭化成ファーマの、産総研は産総研の強みを生かして、その合わせ技でものを造っていくという体制にしました。産総研は発現系構築に対するノウハウやタンパク質の構造解析や機能解析といったところに強みがあり、旭化成ファーマはもともと生産に適する菌株を数多く持っていたので、それを使って実証を進めていった、という感じです。その目的物を造る生産菌をどのように改良するかということについては常にディスカッションし、研究グループ全員で協働して進めていきました。
酒瀬川:旭化成ファーマには歴史的にずっと長く先人から引き継がれた様々な生産菌株がストックされていました。本研究対象のコレステロールエステラーゼはBurkholderia stabilis という菌の野生型生産株を使用していたため生産量が少ないという課題がありました。一方で、本酵素の市場での需要は拡大し続けていたため、従来育種法で生産性の向上が試みられておりましたが、十分とはいえない程度の改善だったため、組換え体へのチャレンジの必要性を強く感じていた矢先に、このプロジェクトの話をいただき、本研究をスタートしました。
生物細胞が持つ物質生産能力を最大限まで引き出すスマートセルのデザイン
酒瀬川:育種の研究を長年積み重ねる中で育種途上の株を捨てずにストックしておいたということがプロジェクトの研究を進める上でも非常に役に立ちました。これらの菌株にあった変異をどのように改変して、スマートセル技術の何をどのように組み合わせて高生産株を構築していくかが、プロジェクトの最初の重要なテーマでした。
小西:私が2012 年に入社したとき、当時上司であった酒瀬川からアサインされた最初のテーマが組換え大腸菌によるコレステロールエステラーゼの発現検討でした。コレステロールエステラーゼは細胞にとって致死性のある酵素なので、生産菌であるB. stabilis 野生株では発現、活性化、分泌が極めて巧妙に制御されたメカニズムで生産されています。そのため、それらのメカニズムを持たない大腸菌での生産は難しいと予想されましたので、非常にチャレンジングなテーマでした。いろいろ工夫を凝らして検討を行ったところ、活性体として分泌発現させることに辛うじて成功しましたが、その量は非常に少なく、「これでは事業化は無理だ」といわれました。その後も数年間、大腸菌だけに限らず、酵母や動物細胞を宿主とした発現検討も行いましたが、発現量は向上せず、結局テーマ自体が中止となりました。それから何年か経ち、このコレステロールエステラーゼの高生産化プロジェクトの話がきた際、巡り合わせに運命を感じ、今度こそは何としても成功させると覚悟を決めて取り組みました。
田村:プロジェクトでは、コレステロールエステラーゼを生産するB. stabilis 野生株を宿主にして、宿主ベクター系を構築するところから始めました。遺伝子発現データをもとに発現制御ネットワークの解析と並行して新規発現プロモーターの設計を展開し、スマートセル技術を用いた宿主の改良に取り組み、今の生産菌の原株を構築していったという流れです。
小西:このプロジェクトでは開始当初から一貫してチーム全員で議論し、緊密に連携をとりながら細かく方向性を決めて進めました。また、各自の専門性を最大限生かし、DBTL サイクルを回しながら進めました。DBTLサイクルとは、宿主のデザイン(Design)、宿主の構築(Build)、構築した宿主の評価(Test)、得られた評価結果の学習(Learn)を1 サイクルとし、これを回すことで迅速に宿主を最適化する手法です。例えば、D 領域の遺伝子改変デザインを行う上で必要であったタンパク質の結晶構造解析などL 領域のデータは構造解析のエキスパートである安武が、また、T 領域における検証実験で必要な多数の生データは村松が担当し取得しました。チーム全員で得られたデータを見ながら様々な観点でディスカッションし、合意形成しながら次の目標に向けた実験をデザインして進めました。
村松:私はこの中で一番遅く、2018 年からこのプロジェクトに主に検証実験担当として加わりました。この時期は、多くの検証を行い、大量の実験データを出すべき段階にきていましたので、長く遺伝子組換えの実験をやっていた経験を買われ、参画しました。
酒瀬川:プロジェクトが始まって、いろいろな形で生産系ができつつあるタイミングで村松が関与してくれて、その検証に携わるところでの貢献は大きく、研究が加速しました。
田村:村松は貴重なウエットデータ、特に菌株の活性に関するデータを数多く出してくれたおかげで、構造解析担当の安武もそれを見ながら、次はどうする、という議論を侃侃諤諤に行うことができました。村松の実験データがあったからこそ、次に何をすべきかの方向性が決まり、ゴールに向かって進めていけた感じです。
安武:私は旭化成ファーマとは別酵素の生産向上に関する研究を行っていた時代からのお付き合いです。当時から酵素の構造解析や変異体をつくってその機能を解析することに長年携わってきました。私の専門は微生物というよりもタンパク質(酵素)で、実際にタンパク質がどれくらい細胞内外に存在するのかという検証や、立体構造をベースにいろいろな変異体をデザインし、その変異体のタンパク質生産能力や活性についての検証は村松のデータを基に多くの議論を行いました。
研究チームの絆と連携から偶然生まれたプロジェクトの成功
小西:多い時には2 週間に1 度、産総研北海道センターにグループ全員が参集してお互いに顔を見て議論を重ねる。このイベントが本当に大事でした。コロナ禍でオンライン(Web)会議に切り替えた期間もあったのですが、議論の深まりがリアル会議とは全然違いました。やはり、人が人と直に会って目を見て話をすることの大切さは研究においても同じだと思います。この北海道ミーティングが功を奏してプロジェクトが成功したと思っています。
田村:2016 年に開始した研究は、プロジェクトの委託ステージから、2019 年に助成事業へと切り替わりました。助成事業に入る前に発現ベクターは既に完成しており、生産量は野生株の約7 倍に上がっていました。それでもまだ事業化には足りず悩んでおりましたが、ある日、あるきっかけで偶然にも生産量が30 倍に上がる菌株が見つかったのです。研究のブレイクスルーポイントといえば、この発見がそれに相当するのかもしれません。研究チームの継続的なディスカッションがもたらした絆と連携がこの偶然を引き寄せました。
小西:物質生産能力を最大限まで引き出すスマートセルのデザインを様々試みていましたが、デザイン案はことごとく失敗していたので、その偶然の発見には、正直いって愕然としました。
安武:運良く、うまく神の手が入ったということではその通りなのですが、ただ、着目していた点があり、これは疑わしい、これは何かあると、情報科学を前提に遺伝子配列とその生産性との関係性をずっと調べていましたので、遺伝子配列のどこかが変われば生産性が突然上がるのではないかという発想の下に地道に調べていった結果であり、その地道な努力が偶然をもたらした感じです。この偶然見つかった高生産株というものが、本研究のキーポイントとなる第3 染色体のなくなった菌株です。
田村:第3 染色体のなくなった菌を見つけたことにも重大なエピソードがあります。従来育種の手法としてNTG やEMS などの薬剤、紫外線や放射線の照射、特定の選択圧をかけた培養や遺伝子交換法などにより変異を誘発する手段があります。私たちが変異株を取得する過程で、あるとき条件を間違えて想定以上のストレスを菌に与えてしまい菌がほとんど死滅してしまいました。しかし、生きていた菌株の中から、生産性の高い菌がいることに気付き、調べたら第3 染色体が抜けていた。その時に盛り上がったのは、高生産性のみならず染色体がなくても菌が生きるということ。この菌には3 本の染色体がありますが、そのうちの1 本が丸々なくなっていたのに生きていました。
安武:実験ミスにより過度の負荷を与えたがゆえに見つけた第3 染色体欠損の株が、実はそれが今回のスマートセルとしての親玉の菌株になっていったということです。
田村:スマートセルの完成型として実際に生産株として利用するまでのストラテジーは、第3 染色体欠損株を即利用することでも良かったのですが、知財確保を視野に原因遺伝子を特定する流れに研究の方向性は向けられました。そこで小西と村松がトランスポゾンを利用して変異を入れて、数千の変異株の中から活性が高くなった株を見つけ出し、それはどの遺伝子に変異が入ることでその生産性が上がったのかを、安武と小西がゲノム解析をしながら見つけていきました。最終的に遺伝子上で同じ変異点が入り生産性が高くなった9 つの株を見つけ出しました。
村松:飛び抜けて生産性の高い菌株が出てきた時は感動的な瞬間でした。発見は偶然だったかもしれませんが、そこをサイエンティフィックにいろいろ実験しながら原因を探り、「だからこうなんだ」という理由が分かり、最終的には着地点に向かって進んでいけたのが良かったです。
酒瀬川:企業の研究であれば、偶然でも生産性の高い菌株を見つけ目的を達成したところで仕事はおしまいだったかもしれません。しかし、産総研との共同研究プロジェクトであったために原因追及までできました。もちろん、プロジェクトの成果として、物質特許を取ることが必要で、遺伝子を同定しなければということもありましたが。
村松:社内だけの研究であれば、このような基礎研究的な内容までは注力できないので、特許化には至らず、ノウハウとして閉じ込めていたかもしれません。
スマートセルの完成へ
田村:スマートセルの構築のキーポイントとして、「発現制御ネットワーク構築技術」、「新規プロモーターの探索技術」、「スマートセル技術を用いた宿主の改良」、の3 つがあり、これらが組み合わさって宿主の改変につながりスマートセルが誕生しました。 1 つ目のポイントである「発現制御ネットワーク構築技術」は産総研の別の情報系の研究者と連携して行いました。タンパク質生産量を上向かせるには、その発現レベルを変える必要があり、細胞の中のRNA の発現量をモニタリングすることで、どういった遺伝子がどういった状態で変化するのか詳細に解析することが必須です。その遺伝子発現と転写活性因子の関連性を調べることが「遺伝子発現ネットワーク解析」です。それを基に転写活性因子の発現を高めてみたり、逆に遺伝子破壊したりして、目的の遺伝子産物の生産量がどう変わるかを追いかけたのですが、転写活性因子をどう改変しても、生産量の変化は認められるものの、実用レベルまで生産量を上げることには至りませんでした。結果的に、「発現制御ネットワーク解析」に基づく解析は最適解ではなかったものの、その知見があったがゆえに、第3 染色体にある生産量増加に関連するターゲット遺伝子は転写活性因子ではないとの結論に達し、転写因子の可能性を排除し、次に進んでいけました。
小西:2 つ目のポイントである「新規プロモーターの探索技術」についてですが、大腸菌など一般的に使用される宿主微生物では使用できるプロモーターが知られていますが、今回全く新しい宿主発現ベクター系を創る必要があったため、使えるプロモーターの情報が全くない状態からのスタートでした。まず、高発現している遺伝子のプロモーターを使えば良い、という仮説に基づいてRNA シーケンス解析をしました。5 つの培養条件、8 つの培養時点からRNA を抽出し、遺伝子発現データを得ました。遺伝子は6,764 個ありましたので、6,764×5×8個の数値データが得られました。そのデータから、どの培養条件でも普遍的に発現する遺伝子を、情報解析技術を駆使して絞り込んでいきました。当初、情報解析やDNA、RNA シーケンス解析は専門外でしたが、このプロジェクトの中で身に付けながら進めました。
安武:最近AI が注目されていますが、データがないと機械学習もできないし、やはり実験データありきだと思います。特に生物は非常に複雑で、限られたデータだけでは全く再現できません。ウエットな基礎データがたくさんあってこそだと思います。
田村:第3 の「スマートセル技術を用いた宿主の改良」のポイントは、先ほどの第3 染色体の話になりますが、原因遺伝子を見つけ、結果として何が起こったかを説明します。発現ベクターを導入した野生株でなぜ一定以上の生産性が上がらなかったかというと、発現ベクターの安定性が悪く、宿主細胞の中ですぐに壊れてしまうからです。しかし、染色体に変異が入って、ある遺伝子が機能喪失することで、発現ベクターの細胞内安定性が著しく高くなり、同ベクターの細胞内コピー数も著しく上がりました。ベクターの安定性というところがキーポイントだったのです。最初思い描いた転写因子とは違う視点で進めたことが、本研究成功の1 つの大きなポイントでした。
事業規模の生産システム構築へ
小西:コレステロールエステラーゼの大量生産はラボレベルではうまくいきましたが、実生産に移行する際にはかなり苦労しました。ラボレベルの数リットルのジャーファーメンターでは問題なく培養できましたが、それを実製造タンクで培養したところ、同じ条件にもかかわらず、培養不良となりました。どのように改善したらいいかを実機を使って検証しなければならず、工場の方々と協力しながら試行錯誤を繰り返しました。その他にも、培養後の精製プロセスにおいても実製造スケールではラボスケールでは起きなかった問題が発生しました。培養・精製に至る全ての工程において、社内のノウハウをフルに活用し、なんとか実製造プロセスを完成させました。
酒瀬川:今回の生産規模での取組みの中でSDGs への貢献という視点もはずせません。CO2 排出量削減、電力消費量削減などありますが、生産量を上げる行為は、SDGs に直結する話であり、現実的にできる、できない議論が起こり課題も生じます。生産量を上げる=SDGs をまずは考えることが必要で、SDGs 抜きでの生産はあり得ないという姿勢が大事です。
産業展開 将来事業へ
酒瀬川:この製品自体の売上、数量、市場拡大規模の目標、の将来ビジョンについて、市場規模は100~200 億円くらいですが、これは最終製品の1 つであるセンサーとしての市場規模です。私たちがつくるのはその原料酵素で、そのうちの何分の1 かになるので、なかなか売り上げの数値目標設定は難しいものになります。血中コレステロール濃度を測定・評価することは人々の健康な生活の維持に関わりますし、最終製品であるセンサーというのは場所を選ばずに測定できますから、そういう市場が上がっていくというのは、SDGs の観点からも理にかなっていると思います。
小西:開発した技術の伸びしろはまだあります。この技術は現時点ではコレステロールエステラーゼに適用していますが、この技術はプラットフォーム技術であるため別の酵素にも展開することが可能ですので、新たな酵素を開発し、売り上げを伸ばしていきたいと考えています。
田村:例えば、血中脂質に限らずですが、スマートセル技術をさらに発展させて、次のターゲットとなるような領域をどうするかは、事業と研究の両面で考える必要があります。スマートセル技術は、代謝系を制御して目的物をいかに増やすかという方向性が多いと思いますが、物質生産には生物の様々な要因が絡むということを、私たちは今回のプロジェクトで改めて認識しました。今回開発した基盤技術や知識は、コレステロールエステラーゼのようなタンパク質の生産のみならず、ほかの菌や代謝系改変への応用展開が可能になると思っています。
酒瀬川:宿主を変えても生かせる技術ができ、これを今後いろいろな形で活用し得るということで、まさにこれは「タンパク質工学技術の産業展開」の未来図といえます。体外診断薬用医薬品というのは、特定のバイオマーカーの濃度を特異性良く測る技術が重要ですが、逆に対象を個々ではなく、全体をふわっと観るという技術を開発し、診断するという方向も考えられます。
田村:「ふわっと観る」という発想は大切で、全体を俯瞰的に観察した上で異なる領域の研究テーマを組み合わせ、融合させることで新しい技術を創出できる可能性があります。そうすると、単純にタンパク質の生産とはいいながら、遺伝子組換え技術のみならず、センシング技術、エンジニアリング技術など私たちの専門領域以外の技術を上手に抱き合わせることで新たな発見・技術創出につながると思います。
安武:今までは別々で動いていた研究領域をうまく抱き合わせ、融合させることによって次の時代を切り拓くために、様々な形でAI が使われ始めています。スマートセルの開発のために、AI の活用を考えることも1 つのポイントです。ただ、私たちの世界で限られた研究領域だけでいうとAI を活用するほどの巨大なデータはありません。もっと大きいデータを扱ってこそAI です。ですから、私たちはAI と情報処理とを分けて考えてきました。今回の研究で活用したのは、AI ではなくあくまでも情報処理技術です。大きな研究資金を得て、ひたすらゲノムを読み込む作業は若干泥臭い部分がありますが、そういうことも必要で、研究の領域や、何をやろうとしているかによっての使い分けはとても大切だと思います。AI が主役となる研究領域は当然あると思いますが、一方スマートセルを構築するために私たちが行ったウエットな研究分野では、まずはやってみる、それで得たデータや情報を冷静沈着に解析する、そして次に進むという、まさにそれが研究のPDCA、DBTL ということだと思います。
酒瀬川:コレステロールエステラーゼは体外診断薬用医薬品用産業としての需要が伸びている酵素で、その成長速度に今回の技術で追いつくことができそうになったことは、研究チームのおかげです。研究が成功して本当に良かったです。
本当に素晴らしい研究チームですね。今回、旭化成ファーマと産総研の共同研究チームで受賞された特別賞は、抗体医薬をはじめ新規創薬モダリティー領域の研究が多く受賞されたバイオインダストリー大賞に、良いインパクトを与えてくださいました。本当に新しい領域を開いた研究であったと思います。多くの研究領域の活性化につながってもらえたらと思います。本日は素晴らしいお話をお聞かせいただきありがとうございました。
(聞き手=JBA広報部 大賞・奨励賞事務局/バイオサイエンスとインダストリー(B&I)誌 第81巻6号)
■第7回バイオインダストリー大賞インタビューはこちら
■第7回バイオインダストリー奨励賞受賞者の紹介はこちら