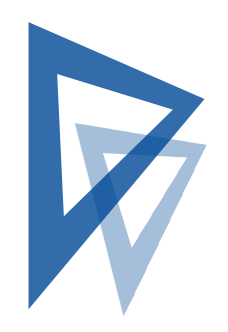第6回バイオインダストリー大賞受賞者インタビュー
 "最先端の研究が世界を創る─バイオテクノロジーの新時代─" をスローガンに創設されたバイオインダストリー大賞と同奨励賞は、今年で第6 回を迎えた。大賞、奨励賞の各選考委員会が6 月に開催され、大賞には、我妻利紀氏をはじめとする第一三共㈱ 技術開発研究チームの業績「新世代抗体薬物複合体DXd-ADC 技術の開発」に対して贈ることが決定され、奨励賞には11 人の若手研究者が選出された。2 年ぶりのリアル面談形式で大賞受賞者に対するインタビューを実施し、研究開発のエピソードや創薬への熱い想いを語っていただいた。
"最先端の研究が世界を創る─バイオテクノロジーの新時代─" をスローガンに創設されたバイオインダストリー大賞と同奨励賞は、今年で第6 回を迎えた。大賞、奨励賞の各選考委員会が6 月に開催され、大賞には、我妻利紀氏をはじめとする第一三共㈱ 技術開発研究チームの業績「新世代抗体薬物複合体DXd-ADC 技術の開発」に対して贈ることが決定され、奨励賞には11 人の若手研究者が選出された。2 年ぶりのリアル面談形式で大賞受賞者に対するインタビューを実施し、研究開発のエピソードや創薬への熱い想いを語っていただいた。
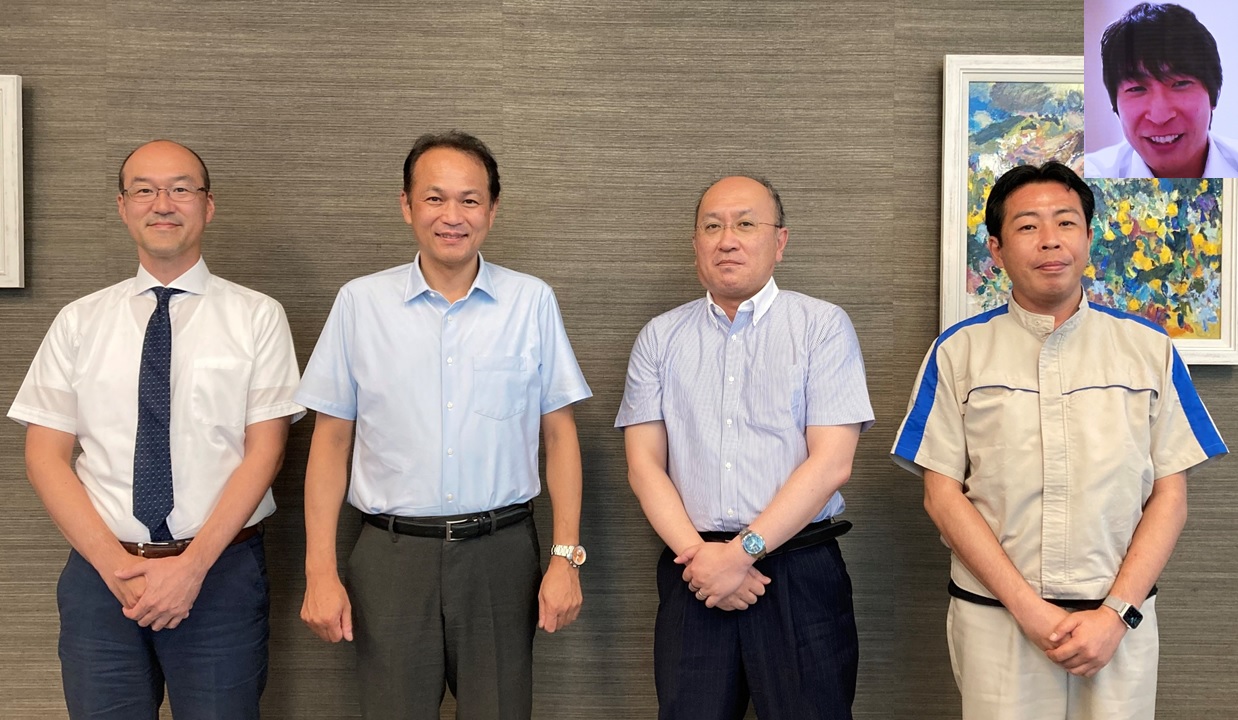
左から阿部有生 氏、我妻利紀 氏、内藤博之 氏、中田 隆 氏、扇谷祐輔 氏
「多くの患者さんに対して貢献できる創薬を」-自分たちの強みを結集し新しいことにチームで挑戦する-
◆この度の受賞おめでとうございます。受賞が決まってのご感想をお願いします
我妻:名誉ある賞をいただくことができてとても嬉しく思っています。特に、一緒に頑張った仲間とチームで受賞できたことをとても嬉しく感じます。
◆今回の受賞はワンチーム第一三共ということで、一企業だけで成し遂げた意義は大きいと感じます
我妻:今回の受賞の要素の1 つに、日本の研究に"ものづくりの力" があることを信じ、きちんと示せたことがあると思っています。当社に育まれてきた"ものづくりの力" が、チームの力によって、このように昇華して成果に結び付くことができたことは、大変嬉しいことです。それと同時に、この受賞を通じ、企業の創薬研究にもスポットが当たり、そういった研究に携わる方々に元気を持ってもらえるものとなれば、なお嬉しいです。一方で、アカデミアの先生にも臨床開発では大変お世話になりました。その意味では多くの人に支えられたオール ジャパンでの受賞であると感謝しています。
◆受賞業績である「新世代抗体薬物複合体DXd-ADC 技術」について、研究を始められたきっかけについてお聞かせください
我妻:21 世紀初頭、海外のバイオ医薬品が急激に成長し、輸入品目の大きな割合を占めてきました。その中で、バイオ医薬品で自社の強みを活かし、患者さんのためになって、かつ世界に打って出るものを真剣に考えなければなりませんでした。我々はADC(Antibody-Drug Conjugate)技術で自分たちの強みを創り、患者さんに貢献しようと、2009 年に検討を開始しました。新領域で、自分たちの強みを集めて新しいことをやろうという機運の高まりの中で、2010 年にこの研究チームに集まったのが今日のメンバーです。
「余命何カ月」という患者さんに対して、平穏な生活を何年も送ることが可能な薬を創りたかった。そう考えたときにADC は非常に魅力的な技術で、人生にポジティブな影響を与え得る薬を創ることに、高いモチベーションを持ちました。1 人ではできませんし、様々な違う専門性を集結させなければなりませんが、当社はそれができる状況にありました。「自分たちの強みを集めて新しいことにチームで挑戦する」、それがチャレンジの根源であると思っています。
阿部:研究はそれぞれ専門性が異なるメンバーが協同で進めました。内藤、中田は合成研究、私はin vitro の評価、扇谷はin vivo の評価、プロフェッショナルが一緒に仕事をするということ、そこがこの第一三共の強みです。我妻がADC をやることを提唱し、研究チームが集められ、その目標に向かって突き進みました。
我妻:「クロスファンクショナル」という言い方になりますが、いろいろな部署から人を集め、形のないところから技術を開発するトライアル的なところから研究を開始しました。
阿部:開始当時、モノクローナル抗体薬は抗がん剤としての有効性に難点があり、開発が芳しくないものが数多くありました。ADC のD にあたる薬物候補として、研究チームが社内で見つけた「DNA トポイソメラーゼI 阻害剤DX-8951」は、第一三共の化合物ライブラリーの中から、様々なメカニズムの候補薬物をいろいろ試した中で、ベストの抗腫瘍活性を示しました。そこで、ADC という、抗体(A)で病巣に的確にDNA トポイソメラーゼI 阻害剤(D)を届ける新しい技術が確立できれば、がんの患者さんに貢献する薬を確実に創ることができると考えました。
◆抗がん剤の市場に敢えてADC で挑戦されたのですね
我妻:研究を開始した頃の、がんの領域における製薬業界のトップニュースは、第1 回バイオインダストリー大賞を受賞された本庶先生の研究成果でもあるオプジーボ®(一般名:ニボルマブ)の優れた臨床試験成績でした。この領域に膨大な研究開発費を注ぎ、臨床開発を進めることが製薬業界のメインストリームで、がん研究=がん免疫という雰囲気の時代であり、その中でADC をやると言いだした時は、「いまさら?」という意見が社内でたくさんありました。一方、我々は学会や論文データ等をつぶさに分析していて、良いものがデザインできるという自信がありました。
扇谷:その当時、世の中にはHER2(がん細胞増殖に関与するタンパク質)発現乳がんを標的にする薬がメガファーマから既に多く出ていた中、それらを凌駕する薬を自社から本当に出せるのかと厳しい意見が多くありましたが、自分たちの薬剤ポテンシャルを信じ、やり遂げることができて良かったと思っています。
我妻:HER2 は乳がんの標的としてとても魅力的であっただけでなく、当時の学会情報を見ると、まだHER2を標的とした治療の恩恵を十分に受けていない患者さんが多くいらっしゃるので、良いものを作れば、大型の製品になる可能性はあると考えました。しかし、我々がこれから創り得るADC の技術がどれだけ優れているかについて、我々の期待値と会社の研究開発シニアの期待値に大きな隔たりがあり、HER2 を標的とするADC の開発を、前面に掲げて進めることは困難でした。そこで、HER2 以外の標的研究を含むADC 技術全般の3年間の研究計画を認めてもらい、研究に専念できる環境を作りました。2010 年のことです。その3 年間の中で、HER2標的でも研究で良いデータが出れば、納得を得ることができると考え、HER2 のADC プログラムも、その中でしっかり進めました。
阿部:基礎研究の後、2015 年に、HER2 のDXd-ADC で、期待通りの有効性がフェーズ1 の段階で確認できました。それがポジティブな結果であったため、それ以降、イケイケドンドンで応援する声が社内で醸成されていきました。
◇データドリブンで革命的な創薬を実現
◆新技術DXd-ADC のキーポイント イノベーションのポイントとは
内藤:新技術DXd-ADC(図)のキーポイントとしては、抗がん作用を持つ化学療法薬DX-8951 を基に、ADC として有効かつ最適なペイロードであるDXd を新たにデザインしたこと、このDXd を遊離させる新規リンカーの設計開発をしたことの2 つが挙げられます。これらを生み出したイノベーションのポイントは、過去のデータを大事にし、良い点と悪い点をきちんと把握する分析力、薬になるものをデザインする想像力、そして実際のものとして創り上げる創造力の3 つになります。昔、強力な薬理活性を持つDX-8951 の研究、また、このDX-8951 を用いた高分子複合体のDDS(Drug Delivery System)研究が社内で行われていました。残念ながら、これらの研究において生み出されたものは、薬にはなりませんでした。しかし、一見失敗に思えたこれらの研究のデータを大切に扱い、その良い点と悪い点を1 つ1 つ丁寧に考察し、そこに新しいエッセンスを加えることで、一気に応用展開が進んでDXd-ADC につながる非常に有用性の高い薬物リンカーができ上がりました。抗体や化学療法薬の研究だけでは上手くいかないことが、社内のそれぞれの専門家が強みを活かし合い、然るべきタイミングで技術を統合させたことが成功のポイントだと思います。チームで研究を行うことの素晴らしさはここにあり、これもイノベーションを起こした重要なポイントの1つと言えます。
扇谷:薬理活性評価に携わる研究者として大事にしていることは、候補薬物の中から良いものを確実に拾い上げるスクリーニング、候補薬物の価値最大化の2 点です。意味のある非臨床データを取得して、それを臨床開発メンバーに共有し、実際に臨床試験のデザインに反映させ ること。今回のADC についても、「ある患者層に対しこの薬はこのような科学的理由から有用である」というアイデア・仮説を出し、検証を進める中で有意義なデータを取得できたことが、結果として適応患者層の拡大、そして大きなイノベーションにつながったと感じています。候補薬物を創製する内藤、中田と、評価を行う阿部と私とが、ディスカッションを密に行い、評価結果をフィードバックし、次の提案をする、といった連続の動きが極めてスピーディーにいったことも奏功しました。研究開発シニアの納得を得る際にも、仮説や理論だけではなく根拠となる研究データを示すことが重要であり、当時は泥臭く膨大なデータを取得しました。
中田:「泥臭くやるべきところは泥臭くやらなければダメ」は大事なキーワードです。ADC の技術開発では、in vivo の動物モデルを使って候補化合物の効果を逐次証明をするという泥臭い仕事の繰り返しが必要で、ADC 技術のキーであるリンカーについても当初はいろいろな選択肢があった。最初からこれにすると結論付けるのではなく、全ての可能性、全ての候補をきちんと試し、結果を皆で議論し、方向性を決めて行った。泥臭い仕事も自分の任務として責任を持って1つ1 つ研究で実践し、解決して行けたところがすごく面白かったです。
阿部:年齢や役職など関係なく言いたいことを話し、仮説として提案する。そして実験を行い、データに基づいて判断する。トップダウンで最初から決めつけず、チームで議論し尽くして出す「作業仮説」を実験で検証し、そのデータに基づいて価値を判断するという「エンピリカルアプローチ」を大事にしています。
我妻:研究者間でコミュニケーションが充分にあると、質の高い実験計画から面白いデータが出て、そこで議論が盛り上がって、次の仮説が出され、さらにトライアルされていく。それが、そこかしこの場面で起こる。「いいものが創れているかどうか」を即座に判断する状況が形成され、データドリブンに、もののデザインの方向性が決まって行きました。
◆ブレイクスルーポイントとは
阿部:研究チームの一員として、うまくいかずに研究テーマが途中で終了する、そういった危機感を持ったことは一度もありませんでした。DNA トポイソメラーゼI 阻害剤で先に進める決定を出したタイミングで、化学合成により詳しい知識を持った内藤が加わって、チーム全体の仕事がしやすくなりました。連続的な動きの中で本技術のキーとなるリンカーのブレークスルーがあり、新ドラッグリンカー技術の発明につながりました。
扇谷:私は当時、入社間もなく、創薬経験が乏しかったため、有望なドラッグリンカーを評価した際、安易に「いけるな」と思ってしまいました。ところがその後、そのドラッグリンカーが候補から脱落。私はこの場面で結構落胆してしまいました。しかし、間髪入れずに内藤や中田がいた化学合成グループが新しいアイデアを次々持ってきて、一気に巻き返しました。その時の「うちの化学合成はすごいな」という思いは、今でもよく覚えています。
中田:扇谷が落胆した最初の化合物は私が提供したものでした。すでに内藤が次の候補化合物を作っているのを知っていたので私は危機感を持っていませんでした。このチームなら何かあっても大丈夫だろうなと感じていました。
内藤:化学合成研究は、世の中にないものを自分で創り上げるという点で、一種「遊び」のような感覚が存在します。自分自身がやりたいことをやって、薬ができ上がるという、こんな楽しい仕事はないとも言えます。つまずいてからもジャンプアップを楽しめるのが合成化学者ではないかと。ですから、扇谷がどこかでつまずきを感じたときでも、「ブレークスルーが生まれるチャンスだ」という発想の転換ができる。化学者は自分たちで、ものをデザインして創るという立場にあるので、そういった楽しみ方をしていたように記憶しています。そして、最終的には良いものにつながったので、私自身は行き詰まりを感じたことはありませんでしたし、やりたいことがやれたという印象が残っています。成功談によくありがちな困難に直面し、悩み抜き、ブレイクスルーポイントに到達した、といったこととは少し違う感覚かもしれません。
◇将来の創薬に向けて
◆新規創薬モダリティー 日本の製薬業界が向かう先とは
我妻:ものづくりに長けている日本の企業が、バイオ医薬品分野で成功事例を出せるようになってきたことは、大きなアドバンスです。バイオ医薬品はまだまだ飽和しているフィールドではなく、いろいろな応用が効く領域で、新しい薬が出てくる領域です。当社も、DXd-ADC 技術開発を通じて、新しい技術を作るプラットフォームや研究プロセスの経験を積みました。これをさらに活用し、別の薬剤を搭載したADC の可能性に挑戦することができます。自社の強みを活かしながら、患者に貢献できるような研究や仕事を残していきたい。また、ADC 技術は、標的のある組織に特異的に薬を送達できるテクノロジーですから、そのメリットは、がん以外にも応用できる可能性があります。
内藤:高齢化が進む中で、就労人口が減り、その労働力を補うための技術進化はさらに加速化されていくと思われます。昨今、創薬と人工知能とのコラボレーションは盛んに行われてきています。今後、人工知能やIT の領域も創薬における注目点の1 つであると考えています。
中田:CDMO(医薬品開発製造受託)の話になりますが、日本の製薬会社の研究開発の継続性の点で、試薬、部品などは、だいたい海外メーカーのものを輸入していることが気になります。バイオ医薬品も国内品で生産ができるようになる仕組み作りが重要と考えます。
我妻:半導体などが代表例ですが、昨今様々な工業製品の部品やその原料の海外からの調達の課題が浮き彫りになってきています。医薬品産業でも多くの原料や部材の調達でいろいろな制限を受けています。グローバルで効率のよい機能分担は良いですが、政治的に不安定なことが起きると、その調達ルートは一気に崩壊していきます。バイオを日本の基幹産業に育てるのであれば、関連する試薬・資材も含めトータルで取り組めると良いと思います。
当社は百年以上の歴史があります。トップクラスの教育を受けてきた人たちが、当社の研究所に来てくれていますが、社会で役立つ研究を生み出せる人材にさらに育っていってもらう必要があります。研究所はそのための道場としての役割があります。研究者はサイエンスの上では平等に意見を言い合う存在です。この道場の中では、お互いが刺激し合いながら創薬研究者として育ち、腕に磨きをかけ、協力して研究成果を出していく。チームの成果が、世の中の多くの患者さんに対して貢献できる仕事に膨らむ。もしかしたら日本の産業を支えられるようなインパクトのある製品になるかもしれません。ここにいると、自分たちのレベルを上げ、世の中に貢献できる人材になれるのではないかと思ってもらえるような、そういう場を提供できるような研究組織が理想です。イノベーターの種として企業に入社した若い人たちが、実際にイノベーターになり、世界に貢献できる1 つのエコシステムの一役を担う。それが一番の社会貢献ですし、アンビシャスかもしれませんが、そうありたいと思います。
-若い人たちへの素晴らしいメッセージだと思います。今日は、本当にありがとうございました。
(聞き手=JBA広報部 大賞・奨励賞事務局/バイオサイエンスとインダストリー(B&I)誌 第80巻6号)
■第6回バイオインダストリー奨励賞受賞者の紹介はこちら