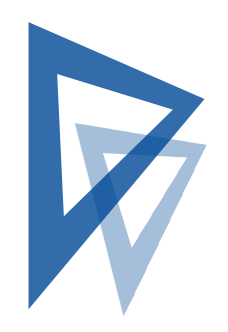第3回バイオインダストリー大賞受賞者インタビュー
 2017年、(一財)バイオインダストリー協会(JBA)は、創立30周年を迎えたのを機に、次の30年を見据えて、"最先端の研究が世界を創る―バイオテクノロジーの新時代―"をスローガンに、「バイオインダストリー大賞」、「バイオインダストリー奨励賞」を創設した。
2017年、(一財)バイオインダストリー協会(JBA)は、創立30周年を迎えたのを機に、次の30年を見据えて、"最先端の研究が世界を創る―バイオテクノロジーの新時代―"をスローガンに、「バイオインダストリー大賞」、「バイオインダストリー奨励賞」を創設した。
第3回となる今年度も6月に大賞、奨励賞の選考委員会が開催され、大賞には東京工業大学名誉教授・理化学研究所名誉研究員 土肥 義治氏ならびに㈱カネカの5名(塩谷 武修氏、松本 圭司氏、松本 健氏、藤木 哲也氏、佐藤 俊輔氏)が選ばれ、奨励賞には10人の若手研究者が選出された。JBA大賞・奨励賞事務局では㈱カネカ東京本社に研究代表者である土肥 義治氏と(株)カネカの松本 健氏、藤木 哲也氏を訪問し、今回の受賞業績である 「海洋分解性を有する生分解性プラスチックの微生物合成系の研究と大量生産技術の開発」の背景と苦労された点、基礎研究への想いや今後の課題等についてお話しを伺った。

4.左から松本氏、土肥氏、藤木氏
左から松本 健氏((株)カネカ 高砂工業所 BDP生産グループリーダー)
土肥 義治氏(東京工業大学 名誉教授・理化学研究所 名誉研究員)
藤木 哲也氏((株)カネカ R&B企画部兼新規事業開発部 幹部職)
「社会のニーズを考えながら、新しい研究課題に挑戦すべき」
◇研究のきっかけはPHAという「忘れられたポリマー」に注目したこと
◆この度の受賞、おめでとうございます。代表して土肥先生に一言 ご感想をお願いします。
土肥:今回この様な大きな賞をいただけるというのは非常にありがたいと思います。最近、バイオインダストリーというとみんなが医薬の方に向いていて微生物関係の産業の影が薄かったと思います。そういう意味では我々のような仕事が受賞できたというのは嬉しかったし、結果的に大学関係の若い研究者への良いメッセージになるのではないかなと思います。
 ◆ 土肥先生が今回の受賞業績である"生分解性プラスチックの研究"に取り組まれたきっかけは何だったのでしょうか?
◆ 土肥先生が今回の受賞業績である"生分解性プラスチックの研究"に取り組まれたきっかけは何だったのでしょうか?
土肥:生分解性プラスチックの研究に取り組み始めたのは1984年からです。折しも私が東京工業大学で化学環境工学専攻の研究室に助教授として就いたころでした。1970年代はプラスチックごみ問題が非常に大きく取り上げられた時代で、そこで何とか高分子と環境を結びつけた研究したいと思い、プラスチックリサイクルの研究を始めようかと思いました。開始してしばらく経ったころ、それでは中途半端であるということに気づき、石油を使わず、バイオマスを使って微生物合成する生分解性プラスチック(バイオプラスチック)に大きく研究を振ることにしました。1年ほど図書館でいろいろ調べて辿り着いたのがポリヒドロキシアルカン酸(PHA)でした。PHAは非常に古いポリマーで1920年代に微生物の中にあるという事がわかっていたのですが、それ以来、長い間「忘れられたポリマー」でした。それをもう一度やろうということで研究を開始しました。その意味では研究の対象が石油のプラスチックからバイオプラスチックに変わっていったというのがきっかけです。
◆ 今回の研究テーマに至るまでに紆余曲折があったようですが、実際にこの研究で土肥先生ご自身が苦労されたことは何でしょうか?
土肥:すぐには成果が出なかったことです。私は比較的早い時期にポリプロピレンの最初のリビング重合触媒を見つけたので、それを学会で発表すると多くの方が聴きに来てくれました。その他にバイオポリマーの合成研究グループを持っていたのですが、こちらには誰も聴きに来てくれなかった。当時、高分子学会で発表した時には、「バイオポリマーはポリマー合成ではない」ということで、学会初日の最初か最終日の発表となり、聴衆がほとんどいなかったですね。その後、1987年に新規のバイオポリマーを作る新たな微生物を見つけ、それがマスコミに取り上げられて学会等でも認められるようになりました。ですから、バイオプラスチックというものの認知度を上げるのが苦労した点です。
◆ 今回の受賞は産学連携ということでも大きな意義があると思いますが、カネカさんと共同研究に至った経緯を教えて下さい。
土肥:高分子学会の反応工学研究会でご一緒していた(株)カネカの野島康弘氏が高砂工業所の生産技術研究所長をされていた1989年に共同研究の打診がありました。その時に私から植物油でPHAを作る研究をしませんかという提案をした。それまではPHAは糖から作っていたのですが、生産性が悪く、それを植物油で作ると生産性が向上するということが理論的に解かってきた。ところが、当時は植物油でPHAを作る微生物があまり知られていなかったのです。カネカさんには植物油を使う工場があるので、工場の近くの土壌から微生物を採取して、共同研究をスタートしたのが1990年でした。今回の共同受賞者の塩谷氏が1991年に新規高分子のPHBHを作る微生物(Aeromonas caviae)をカネカ敷地内の土壌から単離した。このPHBHがプラスチックの素材として非常に物性が良いという事が明らかとなり研究が本格化しました。カネカさんとはもう30年近いお付き合いで、その間、浮き沈みはありましたが、このような長い期間、良く続けていただいたと思います。
◇社内の土壌からPHAをつくる微生物をみつけた。運命的な出会い!
 ◆ PHBHを体内で合成する微生物をカネカ高砂工業所内の土壌から発見し、生産研究を開始したとのことですが、なぜ、自社の敷地内だったのか もう少し詳しくお話し頂けますか?
◆ PHBHを体内で合成する微生物をカネカ高砂工業所内の土壌から発見し、生産研究を開始したとのことですが、なぜ、自社の敷地内だったのか もう少し詳しくお話し頂けますか?
藤木:先程、土肥先生がお話された通り、原料として植物油を用いてPHAを作ると生産性が向上することが分かっていたということと、弊社には食品関連の事業部があり、植物油、マーガリン、魚油も含めて、それらを扱う製造部がすでにありましたので、そういうものを扱っているところの土壌であれば、そこには植物油を原料とする微生物もいるだろうと予見し、その辺りの土壌から微生物の採取をしました。驚くことに、社内外の土壌から採取した約3000余りの微生物から2つの微生物がヒットしました。一般的な微生物のスクリーニングよりも1万倍とか10万倍高く、正直言って信じられないくらいのヒット率で、塩谷氏をはじめ当時の担当者の運も強かったのだと思います。初めにPHBHという有望なものがみつかっていなければ、この研究は続けていなかったかもしれません。そういう意味では運命の出会いだったのかもしれません。
◇遺伝子クローニングの成功がブレイクスルーだった
◆ 一連の研究開発の中でブレイクスルーを遂げられた一番のポイントは何だったのでしょうか?
藤木:最初に研究を始めたのはカネカの生産技術研究所でPHBHという新しい構造を持ったPHAの研究をしたのですが、当時は生産性が非常に低く、一週間培養して10~30g/L程度しかできませんでした。これでは工業化はできないということで、A. caviaeの合成酵素遺伝子のクローニングを試みながら PHBHがどのような物性を有するのか研究を続けたのですが、結果的には弊社では遺伝子のクローニングができませんでした。それが理由で、この研究は一旦中断となりました。ただ、幸いなことに土肥先生との共同研究は継続していました。当時、東京工業大学から理化学研究所に移られた土肥先生の下におられた福居俊昭先生(現 東京工業大学教授)が1996年にPHBH生合成遺伝子群のクローニングに成功され、A. caviaeのPHBHの生合成系の遺伝子の導入ができました。遺伝子がクローニングできたということは、遺伝子組換え技術を使って、野生株ではできなかったような生産性の改良ができるということが示されたわけです。実際、PHBHの生合成系の遺伝子を導入した生産菌は非常に多くの植物油を取り込んで、菌体重量の90%近くのPHBHをつくることがわかりました。土壌から分離した野生株ではできなかったような生産性の改良が育種株であればできるはずだということを土肥先生に示していただいたわけです。それを受けて、弊社としては一旦中断していたテーマが生物化学研究所で復活しました。これがブレイクスルーポイントです。
◆ 基礎研究の成果を応用に結び付ける、すなわち、工業化するにあたってご苦労された点をお聞かせ下さい。
 松本:私はケミカルエンジニアとして培養以降のスケールアップと実際のプロセス構築を担当してきました。PHBHを蓄積した菌体からのポリマー精製に関して、2005年頃までは有機溶剤を用いて微生物からポリマーを抽出しようとしていたのですが、培養の生産性の低さもさることながら、ポリマーを溶媒に溶かしたところで溶解度が5%程度でしかなく、溶媒の回収設備だけでもとんでもない大型のものが必要で、しかも収率も全然上がらないという状況でした。そこで、2006年頃に発想を転換し、ポリマーを有機溶剤で溶かすのではなく、菌体側を溶かして洗い流すことを思いつきました。これを我々は「洗濯プロセス」と言っていましたが、洗濯と同じように菌体成分をタンパク汚れとして洗い、すすぎ、脱水して乾燥するというプロセスに変更しました。一方で、当初は、培養の終わった発酵液をポンプで送ることすらできなかった。何故なら、タンクに送るポンプの軸の部分に一旦溶けた樹脂が固まってしまい、その影響でポンプが壊れたり、液が漏れ出たりする毎日でした。そこから10年以上ですね。現場側からすれば大変な思いをしつつも、良く続けさせてもらったと思います。バイオインダストリーという意味では、発酵がベースになっているため、かつての生物化学研究所で医薬中間体の研究に関わっていた人を中心にポリマーの専門家が加わり、研究者だけでなく、エンジニア、製造のメンバーも一体となって、プロセス構築にこだわり抜いた結果が今につながっていると思います。
松本:私はケミカルエンジニアとして培養以降のスケールアップと実際のプロセス構築を担当してきました。PHBHを蓄積した菌体からのポリマー精製に関して、2005年頃までは有機溶剤を用いて微生物からポリマーを抽出しようとしていたのですが、培養の生産性の低さもさることながら、ポリマーを溶媒に溶かしたところで溶解度が5%程度でしかなく、溶媒の回収設備だけでもとんでもない大型のものが必要で、しかも収率も全然上がらないという状況でした。そこで、2006年頃に発想を転換し、ポリマーを有機溶剤で溶かすのではなく、菌体側を溶かして洗い流すことを思いつきました。これを我々は「洗濯プロセス」と言っていましたが、洗濯と同じように菌体成分をタンパク汚れとして洗い、すすぎ、脱水して乾燥するというプロセスに変更しました。一方で、当初は、培養の終わった発酵液をポンプで送ることすらできなかった。何故なら、タンクに送るポンプの軸の部分に一旦溶けた樹脂が固まってしまい、その影響でポンプが壊れたり、液が漏れ出たりする毎日でした。そこから10年以上ですね。現場側からすれば大変な思いをしつつも、良く続けさせてもらったと思います。バイオインダストリーという意味では、発酵がベースになっているため、かつての生物化学研究所で医薬中間体の研究に関わっていた人を中心にポリマーの専門家が加わり、研究者だけでなく、エンジニア、製造のメンバーも一体となって、プロセス構築にこだわり抜いた結果が今につながっていると思います。
◆ 今回受賞されたテーマは、世界レベルで取り組むべき壮大なものだと思いますが、今後の展望についてコメントをお願いします。
土肥:その前に、海洋汚染の問題とこのポリマーとの関わりについてお話させて下さい。海洋汚染防止法については1980年代に国際的に議論されました。その中でマルポール条約、これは船舶による汚染を防止する国際条約で、日本は1987年に生分解性の漁網を開発すべきということで、私の研究室において1990年から1998年に水産庁からの委託研究で生分解性漁網に関する研究開発をしていました。
もう一つ、廃棄物に関するバーゼル条約、これは有害廃棄物の国境を越える移動等の規制についての国際条約で、日本は1993年に加盟しています。この条約ができたのは欧州の事情です。当時、西ドイツは廃棄物全体の約30%を東ドイツに輸出していて、1989年に東西ドイツを分断していたベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一した際に統一した国の真ん中にごみの山があった。これにはドイツ人だけでなく、欧州の人が相当ショックを受けたようで、自国で出たごみは自国で処理しようというコンセンサスができはじめた。それがバーゼル条約につながりました。
ところが日本で海洋汚染、プラスチックごみ問題が浮上してきたのは、2017年に中国が海外からのプラスチックごみ輸入を禁止してからです。日本のプラスチックごみは年間約900万トン、その内の約150万トンを輸出していた。各国で処理しきれないプラスチックごみの一部が海洋に流れ出て海洋汚染を引き起こしたのではないかと疑われ、それが今回のG20大阪サミットでの議論にもなっていると思います。
やはり、ごみ問題の基本は「自国のごみは自国で処理する」ということだと思います。ただ、海に流れ出るごみがなくなるかというとそうではなくて、特に漁網は今でもかなりの量が海に流出しています。ここは生分解性魚網に変えていかなくてはいけない。今のところ海洋分解性を有する生分解性プラスチックはPHBHだけなので、貴重なポリマーだと思います。長い時間をかけて海洋分解性を有する生分解性プラスチックの研究をしてきましたが、これが海洋汚染問題の解決に向かえば良いと思います。
松本:ポリエチレンもポリプロピレンも素材として悪いわけではなく、処分の仕方が悪いだけです。PHBHは海洋分解性ポリマーですが、だからといってむやみに海に廃棄しても良いわけではない。とはいえ、現状はどうしてもごみとして出てくるものもあるので、使い方と社会的インフラ整備の歩調を合わせることで最適な答えが見つかると思います。一つの例として、PHBHは海洋分解性だけでなく、嫌気条件下でも十分に分解するというのが特徴ですので、生ゴミを入れる袋としてそのまま一緒に嫌気処理してエネルギー回収するようなインフラ整備と併せて、PHBHの用途が広がれば良いと期待しています。

◇ とにかく好奇心をもって、自分に限界を設けずにやって欲しい!
◆ 最後に、JBA では、若い研究者を支援する活動も行っています。次世代を担う研究者たちにメッセージをそれぞれお願いします。
土肥:私の研究室からは多くの若い人が育っていて、20名以上が国内外の大学で教授、准教授をしていますが、彼らには常に新しい研究にチャレンジして欲しいと言っています。特に若い人たちには社会のニーズを考えながら、新しい課題に挑戦して欲しい。そのことが結果として学術の幅を広げると思います。そのために何をやるかということですが、新しい課題を見つけるためには一度は図書館にこもって古い論文を読んで欲しい。人間が考えることはそう変わりませんので、図書館には古い時代に諦めた良いテーマがたくさん眠っている。その当時の科学技術では課題が解決できなかったが、今は技術の進歩によってその課題が克服できるものもたくさんあると思います。
藤木:世の中の技術は進歩しても、それは手法が代わるだけの話であって、研究者としての考え方は大きくは変わらないと思います。ですから頑張れる間は頑張ってみても良いと思います。ただ、弊社の若手研究者には、PHBHの研究に縛り付けるつもりはないし、やりたいテーマを自ら見つけ、提案し、幾つかのテーマを掛け持つことも良いと指導しています。いずれにしても、視野を広く、いろいろなことに挑戦してもらえたらと思います。
松本:若い人には、とにかく好奇心をもって、自分が面白くなるように、自分に限界を設けずにやって欲しいと思います。例え結果が出なくても、やったことは無駄にはならないと思います。
―心に響くメッセージですね。若い人たちが勇気づけられると思います。今日は、本当にありがとうございました。
(聞き手= JBA 広報部 大賞・奨励賞事務局 田中雅治)
■第3回バイオインダストリー奨励賞受賞者の紹介はこちら